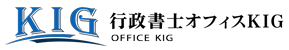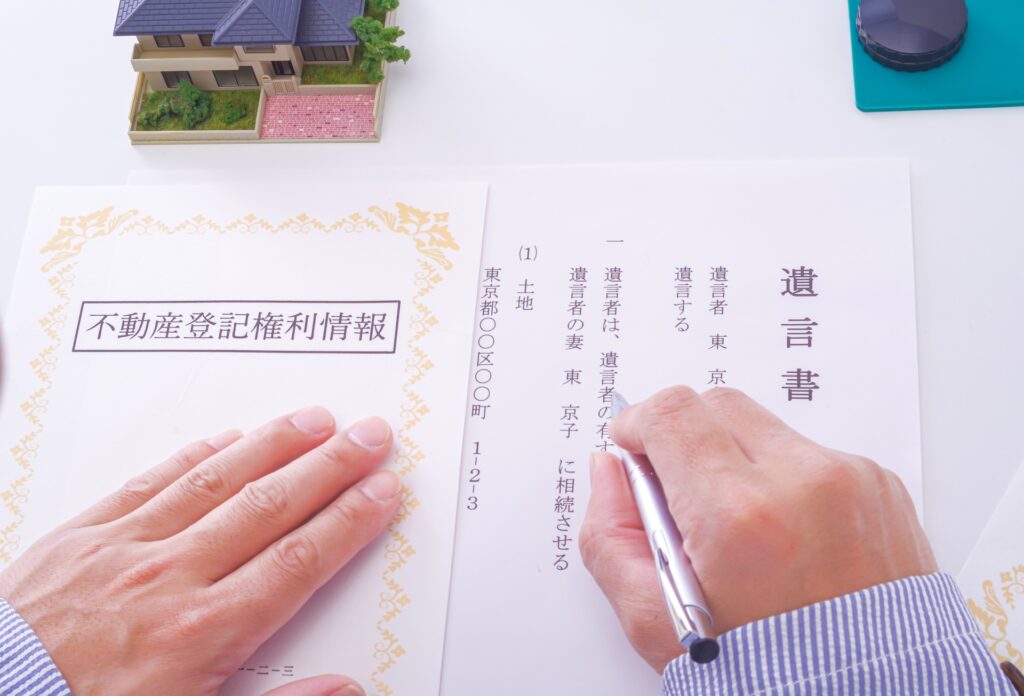
1.子どもがいない夫婦
よくある勘違い → 『うちは子供がいないから、俺が死んだら全ては妻に…』
ほんとにそうですか?
子どもがいない場合、配偶者だけでなく、亡くなった方(被相続人)の親や、兄弟姉妹も法定相続人となります。争いに発展しまい、配偶者が老後を過ごすはずの家を手放さなければならなくなる危険も無視できません。残された配偶者の生活を守ためにも、遺言書で意思を明確にしておく必要があります。一度相談されることを強くお勧めします。
2. 法定相続人以外に財産を残したい
よくある勘違い → 『妻とは籍を入れていないけど、みんな分かってくれているから…』
ほんとにそうですか?
法定相続人ではない人、例えば内縁の配偶者、長年介護してくれた子どもの配偶者、友人、恩人、孫、兄弟姉妹、慈善団体などに財産を遺したい場合は、遺言書が必須です。
法定相続人の全員が賛成しても、そもそも法律上、法定相続人以外の人に相続させることはできないのです。
3.相続人同士が不仲、または相続関係が複雑
兄弟姉妹や親族間で仲が悪い、再婚して片親違いの子どもがいる、行方不明の相続人がいるなど、相続人間のトラブルが予想される場合は、遺言書で分割方法を指定しておくと紛争防止になります。
たとえ兄弟姉妹の関係が良好でも、日頃の行き来があまりない親族とは連絡を取るのに時間が掛かりがちです。さらに、いざという時に仕事等の都合で遠方にいる、あるいは海外にいる、といった場合は考えられないでしょうか。
病気や怪我により療養中で意思の疎通が困難な家族がいたらどうでしょうか。
相続の手続きに予想以上に時間が掛かったり、余計な費用が発生したり、また、相続税の申告期限を過ぎてしまうことにより、税制上の優遇措置等を受けることができなくなり、多額の税金を払わざるを得なくなることもあるのです。
遺言さえあれば避けることができたはずの問題です。
4.主な相続財産が不動産
金銭であれば平等に分けることが容易ですが、不動産となるとそうはいきません。
土地と建物を兄弟二人で等分する、などということはほとんどの場合不可能ですから、話し合いでまとめることも大変です。
遺言書で分け方を指定しておくとともに、少しでも分割し易くするために、財産の整理、組み替えや、保険の活用も検討してみてください。
5.事業・家業の承継が必要
会社や個人事業を営んでいる場合、後継者への引き継ぎをどうするかという問題があります。跡目争いが生じたり、事業の継続に必要不可欠な資産が分散してしまったりすることで、順調だった事業が一転する危険も考えられます。誰に引き継がせるのか、そのためには何を残さなければならないのか等、十分に検討した上で、遺言書で後継者や分割方法を明記しておくことをお勧めします。
6.特に援助が必要な家族がいる
障害や病気などで特別な配慮が必要な家族がいる場合、自分がいなくなった後の生活設計等のために多めに財産を残したい、あるいは特定の財産を残したい場合、遺言書でその旨を明記しておく必要があります。
また、子供がまだ小さい片親家庭の場合、最後に親権を行う者(単独親権者)となる人は、遺言により未成年後見人を指定することができます。その子の監護、養育、財産管理を誰に任せたいのか、遺言でその人を未成年後見に指定しておくことことにより、自分自身に万が一のことがあった場合に備えることができます。
7.相続人がいない
相続人がいないと財産は国庫に帰属します。
しかし、老後何かとお世話になった(あるいはなるであろう)友人、恩人、介護施設、慈善団体、あるいは応援したい団体や、寺院や教会などのコミュニティーに幾らかの財産を遺したい場合は遺言書が必要です。
おひとり様の終活では、遺言とともに死後事務委任契約を結んでおくなどして、自分にもしものことがあった時に必要となる諸手続きや葬儀をあらかじめ依頼しておくことも欠かせません。
その他にも、遺言で出来ることには「相続人の廃除、廃除の取消し」「信託の設定」「遺言執行者の指定」「婚外子の認知」「祭祀承継者の指定」「生命保険金受取人の変更」なども挙げられます。
遺言書は、相続に関するトラブル防止だけでなく、諸手続きの負担の大幅な軽減にも効果があり、また、自分の意思を確実に反映させるためにも重要な書類です。ここまで考えてきたようなケースでは、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

無料相談
Consultation